- 写真のノイズが気になる
- 写真がなんかザラザラしている?
写真を撮っているとどうしても気になってくるノイズ。
最新のカメラは高感度耐性も上がっていてノイズもうまく処理してくれるとはいえ、YouTuberみたいにそんなポンポンカメラ買えないよ・・・。
そんな悩みを抱えている人へ僕なりの考えをシェアしたいと思います。
僕も夜のスナップやスポーツ撮影時、特にナイターの試合なんかはどうしてもノイズとの戦いになります。
そんなときに気をつけている点を写真を撮る前と撮った後に分けて紹介していきたいと思いますのでぜひ最後まで読んでみてください。
写真のノイズ対策はこうしよう【撮る前と撮った後】
写真のノイズ対策には以下のようなものがあります。
- 写真を撮る前に対策する方法
- ・ISO感度を上げすぎない
- ・シャッタースピードを上げすぎない
- ・絞りを開放する
- 写真を撮った後に対策する方法
- ・RAW現像で処理する
大体こんな感じです。
一つひとつ解説する前に写真にノイズが出る原因を知っておくとより理解が深まると思いますので次にノイズが出てしまう原因をサラッと解説します。
写真にノイズが出る原因
写真にノイズが出る原因はひとつで『ISO感度が高過ぎる』ことです。
ISO感度とはカメラで写真を撮る際に写真の露出(明るさ)を決める3つの要素「三値」のうちの一つです。
他に「シャッタースピード」「絞り(F値)」というものと組み合わせて写真の露出を決めています。なのでシャッタースピードが高い・F値が大きいという撮影状況ではどうしてもISO感度が高くなってしまいます。
なのでISO感度を上げ過ぎない設定にするためにシャッタースピードと絞りで調整していくというのが主な対策となります。
暗い場所や動いているものの撮影などではどうしてもシャッタースピードを自由に設定することが難しいというケースもありますが、そうした場合はF値が明るいレンズを使ったり、可能ならフラッシュ(ストロボ)を使うことをおすすめします。
ノイズには大きく分けて2種類ある
そしてノイズには2種類のものがあります。
- 輝度ノイズ
- カラーノイズ
輝度ノイズは一般的にノイズと言われているあのザラザラした感じになるノイズのことですね。
少し専門的な話になりますがデジタル写真は明るさのチャンネルと色のチャンネルで構成されています。Labカラー(エル・エー・ビーカラー)と呼ばれる概念です。
このうち明るさのチャンネルで発生するノイズが輝度ノイズと呼ばれています。
原因はISO感度を上げたことによる電気的な負荷が強まったことで、音響などのボリュームを上げすぎるとジィィィとノイズが入ったりするのと同じ様に写真にもノイズが入ります。
もう一方のカラーノイズは色のチャンネルにノイズがのることで偽色なんて呼ばれています。

その名の通りあるはずのない色が写真に出てしまうことで輝度ノイズに比べて良く見ないと分かりにくいかもしれません。
先ほどのLabカラーのうち、LはLightning(輝度)、aは赤/緑、bは青/黄の色を担当していますがそのa・bいずれかにノイズが発生してしまう現象です。
いずれもカメラの設定である程度軽減させることも可能ですし、RAW現像の際に処理することも可能ですが、一番はノイズが出にくい設定で撮影するということですかね。
写真のノイズを撮る前に防ぐ方法

ではノイズが出ないようにするためにはどんな点に注意すればいいのかを解説していきますね。
写真を撮る前にノイズを防ぐ方法は主に3つで以下の点があります。
- ISO感度を低めに設定する
- カメラのノイズリダクションをONにする
- ライトまたはフラッシュ(ストロボ)を使う
いずれも有効な対策ではありますが、ライトまたはフラッシュ(ストロボ)を使うというのはちょっとハードルが高いかもしれません。
ひとつずつ解説していきますね。
ISO感度を低めに設定する
まずは原因であるISO感度の設定を低めにするというものですが、ノイズの出やすいISO感度というのはカメラによって様々ですが、一般的に1600を超えたあたりから気になるというケースが多いようです。
比較的新しいカメラや高額なハイエンドモデルであれば6400や12800でも気にならないということもありますが、多くの人が使っているコンデジやエントリークラスの一眼カメラであれば大体1600~3200くらいからノイズが目立つようになると思います。
なのでISO感度の設定を極力1600前後で抑えられればノイズを抑えることができます。
ISO感度を必要以上に上げないためには適正なシャッタースピードに設定するということがポイントです。
適正とは早すぎず遅すぎずというスピードで、例えば1/125で十分な撮影状況なのに1/2000に設定していたりすると必要以上に高いISO感度になってしまいます。
なので自分の使っているレンズの焦点距離の倍のシャッタースピードになっていれば十分で、最悪焦点距離と同じ分母のシャッタースピードにすればOKです。
補足:適正なシャッタースピードは『 レンズの 1 / 焦点距離分 』とされていますが、今の高解像度なデジタルカメラではより敏感にブレを検知するので僕は焦点距離を倍にした数値を分母にしています。
例)200mmレンズの場合:1 / 400
あとは絞りを一番小さい数値にして撮影することですね。
表現によっては絞りももっと大きな数値にしたいという時もありますし、動いているものを撮影する際はどうしても高いシャッタースピードでなければ撮影できないというケースもあります。その際はノイズよりもブレないことを優先してISO感度はガンガンに上げちゃってOKです。
なのでこの後解説するカメラのノイズリダクションを使ってできるだけ目立たないようにしましょう。
カメラのノイズリダクションをONにする
カメラのノイズリダクションとは、カメラに搭載されている機能でメーカーによってはノイズ低減やノイズリダクションと呼称は様々ですが多くの場合はその度合いも弱・中・強などで調整できるようになっていると思います。
その機能をONに設定して撮影すれば高感度で撮影した写真でもノイズを極力目立たなく処理してくれます。超便利です。
僕は極力ノイズリダクションをOFFで撮影することが多いですが、デフォルトでは多分ONになっているはずなのでご自身のカメラを一度確認してみてくださいね。
ただノイズリダクションもデメリットはあります。
それは処理に時間がかかるので次の撮影まで少し時間がかかるという点です。
これはナイタースポーツの撮影なんかではかなり致命的な現象でして、連写で撮影したりすると次の撮影までカメラが処理で固まってしまいます。
そうなるとシャッターチャンスを逃しますので僕はOFFにしておくことが多いです。
そうした用途ではなければ一般的には十分綺麗な写真に仕上がるので使ってみて判断するのがいいですね。
ライトまたはフラッシュ(ストロボ)を使う
最後は場合によっては使えないことも多いのですが、ライトを当てて撮る、またはフラッシュ(ストロボ)を使って撮影するという方法です。
写真にノイズが出ないように低いISO感度にするためにはシャッタースピードや絞りをできるだけ明るく設定する必要があります。
それが出来ない環境下ではISO感度をガンガン上げてノイズも表現のひとつと割り切るか、もしくは強制的にその場所を明るくするしかありません。
旅行先で記念撮影をする際はOKだと思いますが、水族館などの中ではフラッシュ禁止となっているところがほとんどですし、その場のマナーをしっかり確認する必要があります。
使用できそうならカメラに搭載されている内臓フラッシュでも十分綺麗に写すことができますし、本格的に撮影したいという場合には別売りのクリップオンストロボ(カメラの上に装着できるタイプ)なんかも有効です。
フラッシュ撮影はちょっとテクニックというか知識が必要ですが、今のストロボはTTLタイプもあるのでカメラで露出を設定すればそれに合わせて発光量をオートで設定してくれますのでめっちゃ便利ですよ。ちょっと高いけど・・・。
屋外での集合写真なんかでも顔に出来てしまいがちな影を弱めてくれたりしますのでひとつ持っておくと重宝します。
写真のノイズを撮った後に消す方法
次に写真のノイズを撮った後で処理する方法ですが、先ほど紹介した方法でも対応できない場合はRAW現像で処理するしかありません。
ここでRAW現像というキーワードが出ましたが、RAW現像というのは写真データを自分で編集してJPEGデータにアウトプットすることです。
スマホで写真を撮ると、スマホ自体が撮った写真の色味やシャープネスを自動で処理して写真にしています。その過程を経ずに撮れた生のデータをRAWデータといいます。
少し専門的な話になりますが、JPEGデーは8bitに圧縮されていますので1,677万色で再現されているのに対し、RAWでは12~14bit(約680億色~約4398億色)の情報量を持っています。
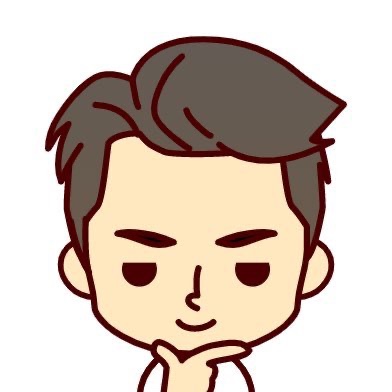
もう意味わかりませんし、肉眼では正直見分けがつかないほどの諧調を持っています。
最終的にJPEGにアウトプットする際には8bitになりますし、そもそもモニターが8bitまでしか表示できないものが多いのでそんな情報量なくてもいいのではないかと思うかもしれませんが、リッチな情報元から作られたデータともともとそれしかなかったデータでは色の表現力がまったく違いますのでこれは実際に確認してみて欲しいです。
分かりやすく表現すると本当は朱色が表現したいのに赤かオレンジしかないからとりあえず赤で表示しておくのと、朱色の絶妙な色合いがあるからそこを使うのとではまったく違いますよね。(分かりにくい?)
絶妙な色のグラデーションや陰影のなだらかさを表現するには極力リッチなデータでなければ表現できないことが多いということですね。
RAWデータで撮影しておくことでそれが可能となりますのでノイズの処理もより綺麗にできるようになります。
ノイズの処理もこのリッチなデータを修正する方がディテールも保持したまま修正することが可能です。ディテールとは例えばまつげや髪の毛の束感などの繊細な部分のことで、ノイズは髪の毛や影の濃い部分などの暗い場所に出やすいのでRAWデータから修正した方が綺麗に仕上がるというわけです。
写真のノイズを消すことができるソフト
ではノイズを処理することができるRAW現像ソフトとはどのようなものがあるかというと有名なところでは以下のようなものがあります。
- Lightroom
- Luminar neo
- SILKYPIX
- メーカー純正ソフト
僕が使っているのはLightroomというAdobe社のものですが、たぶん利用者数では一番多いと思います。プロでも使っている人は多いようでとりあえず入門には一番適しているかなと思っています。
最近ではLiminar neoというソフトも台頭してきていてAIを使ったノイズ処理がめちゃくちゃ優秀でした。
実際にこれは使った経験から言えますが、単純にノイズ処理でいったら現状Luminar neoのノイズレスAIが一番優秀だと思います。
LightroomでRAW現像したい場合は課金が必要ですが、他のソフトに比べれば良心的な価格なので僕が使っている理由のひとつでもあります(笑)
バックアップも1TBあるので一石二鳥です。
各種RAW現像ソフトを比較した記事はこちら
まとめ:写真のノイズはあってもいい
結論としては「ノイズは無理して処理する必要はない」
ということになります。
ここまで長々と書いてきたなんじゃそりゃと言われるかもしれませんが、ノイズがあるから立体感が出るという考え方もあるんです。
デジタル写真は細かいドットで出来ています。2400万画素のカメラで撮った写真は約2400万ドットのピクセルで構成されているということです。
そしてノイズを処理するということはノイズが発生している周辺のピクセル(ドット)を平均化してしまうということなので、細かい線や質感も塗りつぶされるということなのでどうしてものっぺりした感じになるんですね。
Lightroomの無料プランでもJPEGデータなら編集できますのでちょっと試して欲しいんですがノイズ軽減を一番強めにかけると塗り絵みたいなつるつるした絵になってしまいます。

なので僕はノイズ軽減は使っても40~50くらいまでと決めて使っています。
それでもノイズが気になるようでもそのままにしています。スマホで見る限り気にはなりませんし、拡大してじっくり見る人なんてカメラマニアしかいませんから(笑)
なのでノイズは多少あっても全然OKですが改めて対策としては
- 写真を撮る前に対策する方法
- ・ISO感度を上げすぎない
- ・シャッタースピードを上げすぎない
- ・絞りを開放する
- 写真を撮った後に対策する方法
- ・RAW現像で処理する
という形で締めさせていただきますね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
このブログではカメラや写真に関する情報を発信していますのでぜひ他の記事も読んでいただけると嬉しいです。
それではまた別の記事で!
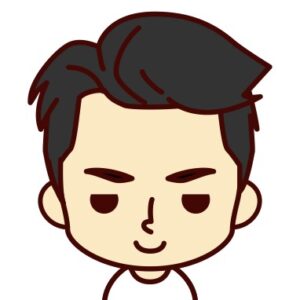
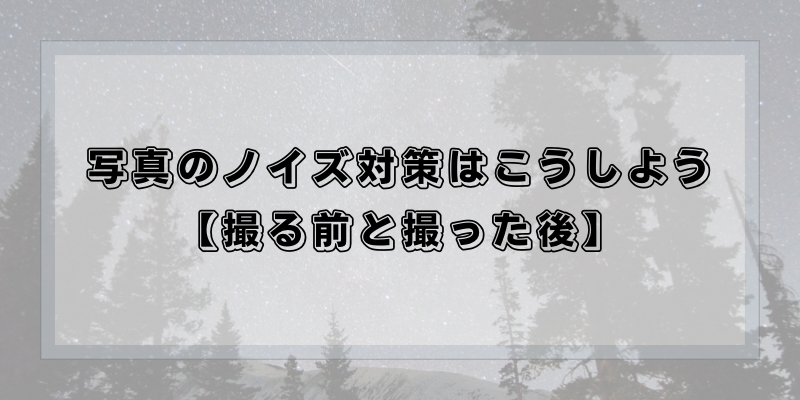
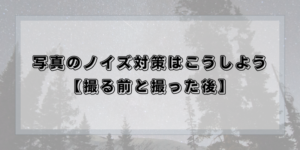
コメント